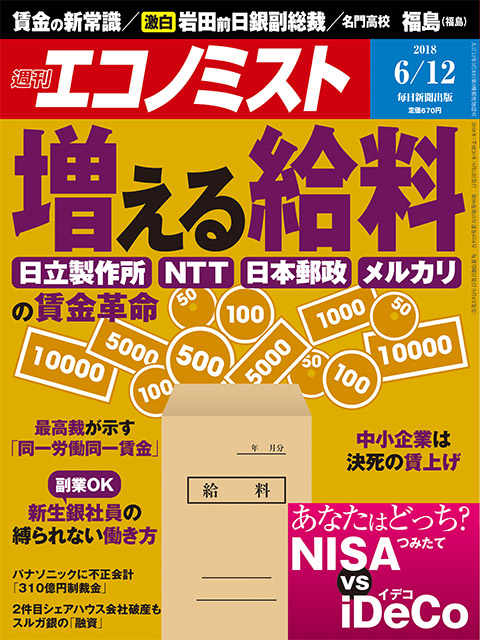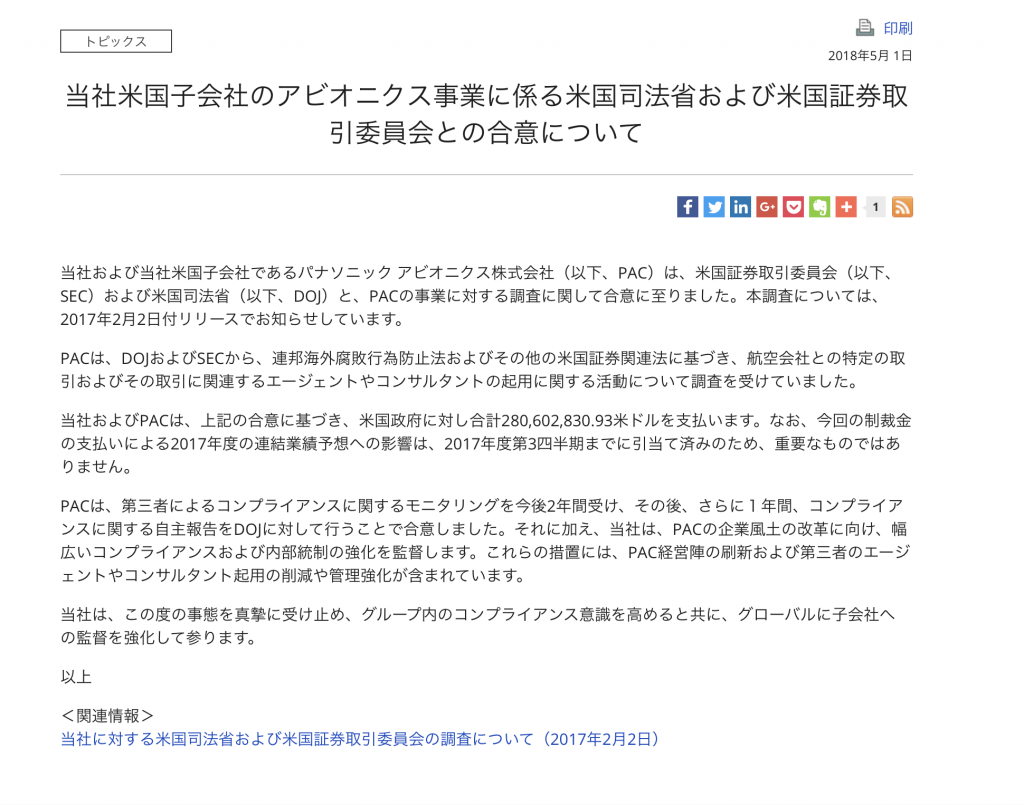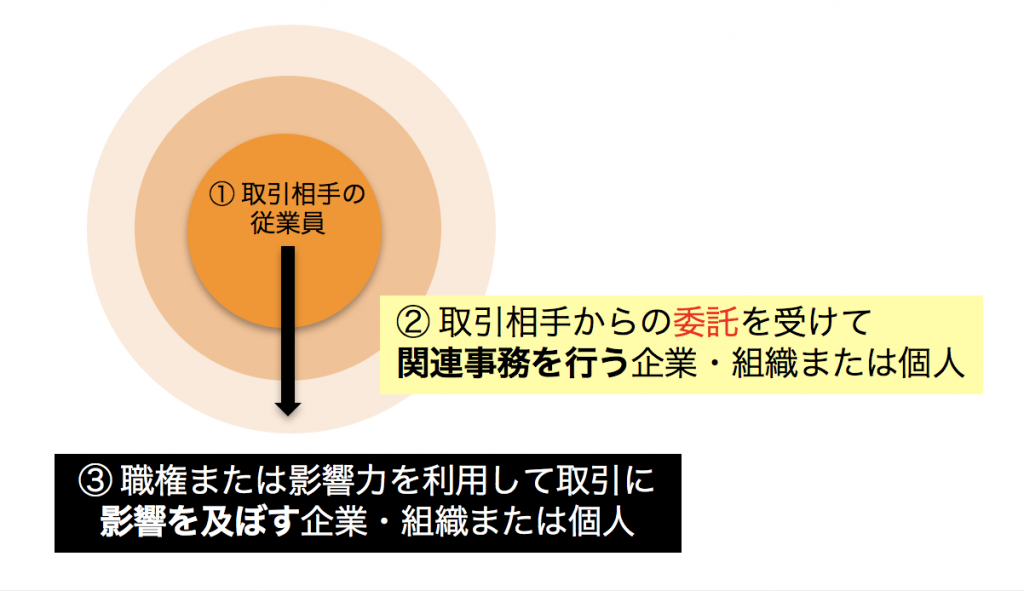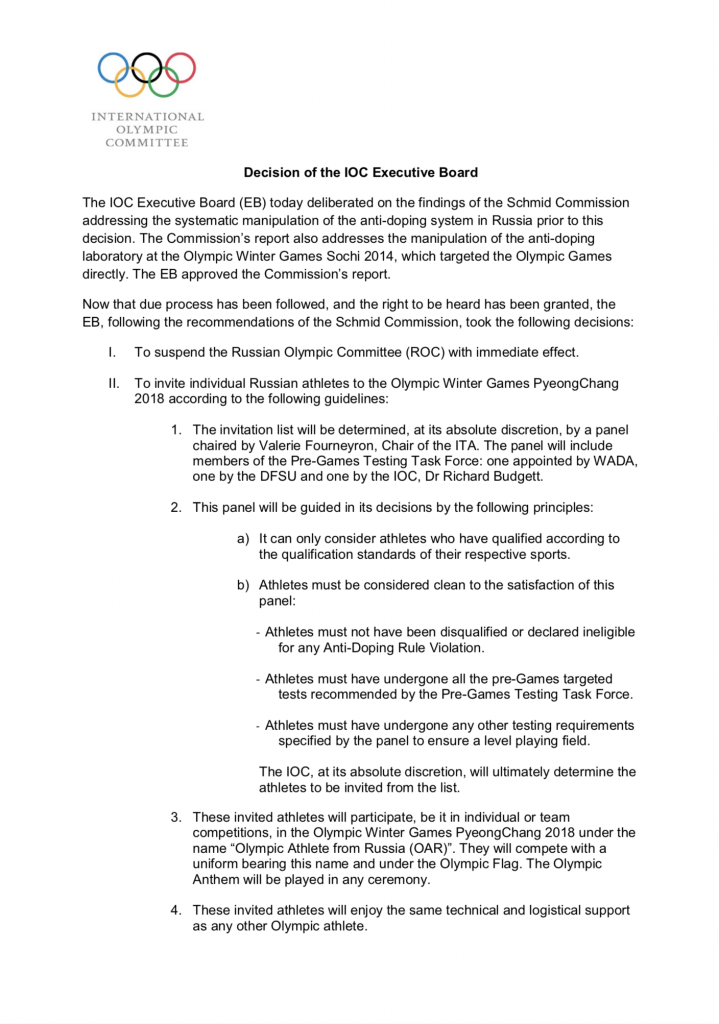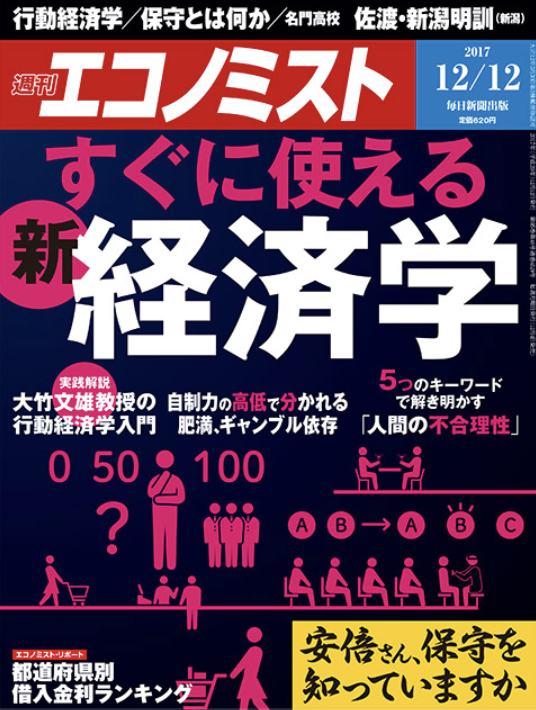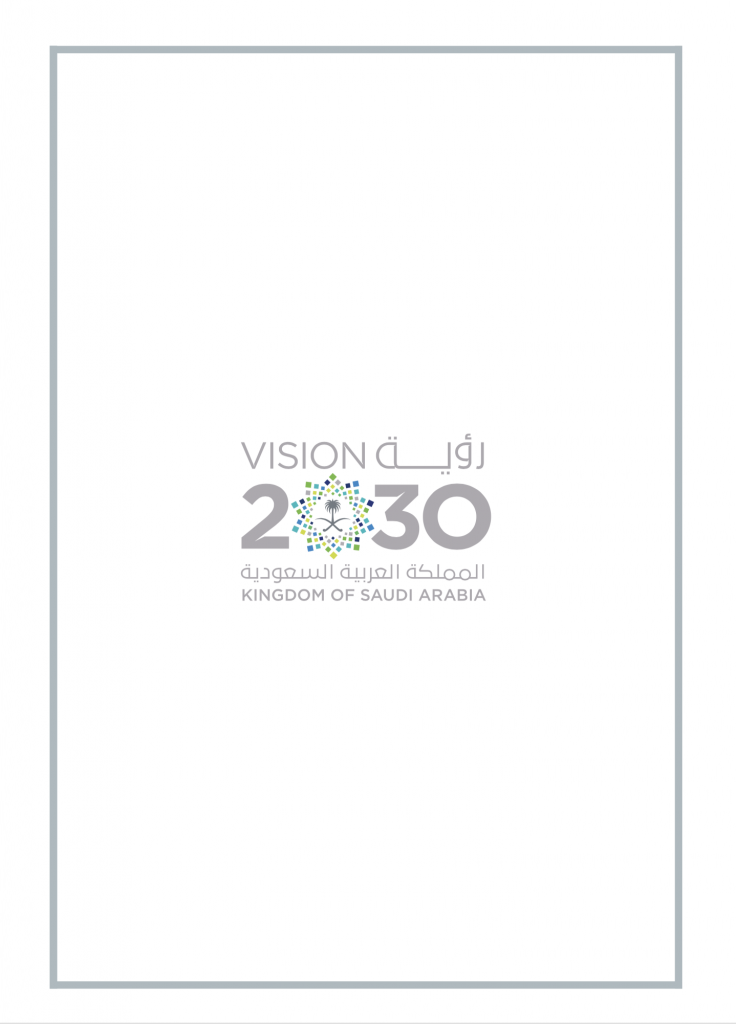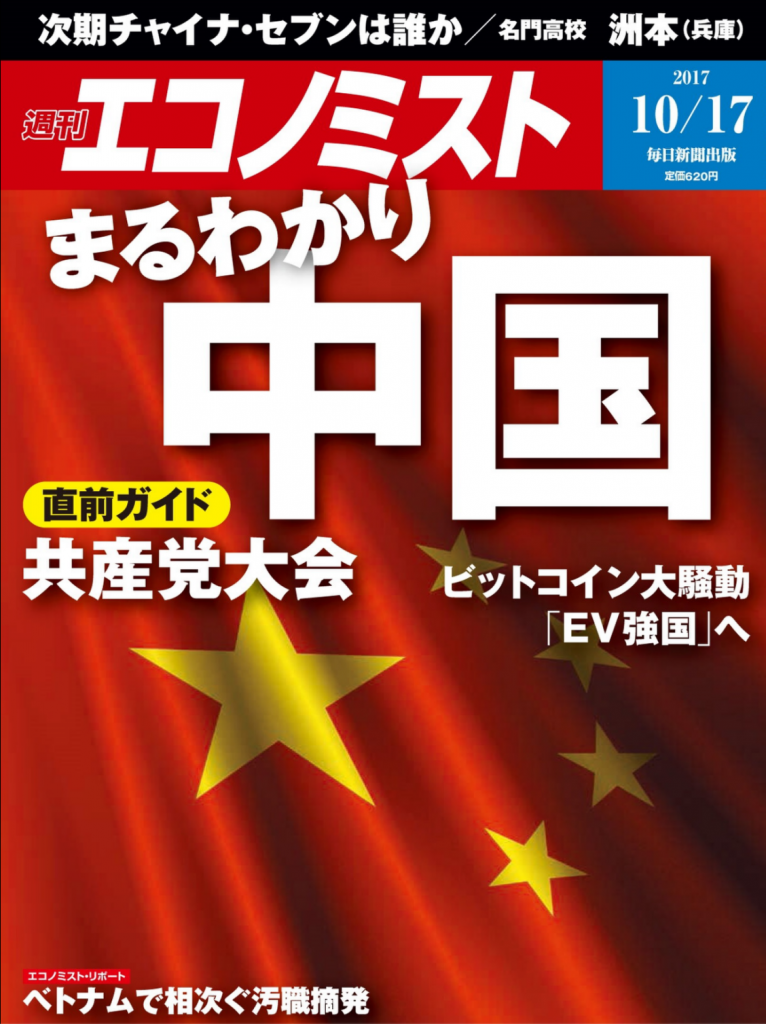本日(6/15)の早朝、テロ等準備罪法案(いわゆる共謀罪の趣旨を取り組んだ組織犯罪対策処罰法改正案)が参議院本会議にて可決され、成立しました。
賛成165票、反対70票。「牛歩戦術」をとった野党議員3名の投票が議長の議事整理権(国会法19条)に基づく「時間制限」を超えたため、投票しなかったことにされました(「無効」ではありません。ちなみに他に4名の議員が投票していません)。

今回の法案採決の手続きで注目を集めたのが、法務委員会での採決を経ないで本会議で採決をするという、「中間報告」という手法。これは、国会法第56条の3が規定している手続きです。
国会法第56条の3
各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
○2 前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。
第1項は、審査を付託した委員会で審査をしている最中の案件について、特に必要があるときに、その段階での審査状況の報告を求めることができると規定しています。これが「中間報告」です。
そして、その中間報告があった案件は、「特に緊急を要する」と認められる場合、議院の会議(つまり本会議)で審議することができると、第2項が規定しています。これが今回用いられた手続きです。
国会法の規定によれば、「特別な緊急性」という要件の認定主体は「議院」ですから、すなわち、議院による判断が下されれば、中間報告を踏まえた本会議での審議(採決を含む)が出来るという制度設計がなされていることがわかります。
実際に今回の法案審議では、6/15深夜(2:31開始)の本会議でまず①「中間報告を求めることの動議」が提出され、3人の参議院議員(民進・藤末健三議員、共産・辰巳孝太郎議員、維新・浅田均議員)による討論を踏まえて採決がなされました。結果は、
白色票(賛成) 百四十八票
青色票(反対) 九十票
で可決されました。次に、②法務委員長(公明・秋野公造議員)が中間報告を行い、続いて③「中間報告があった本改正案を直ちに審議することの動議」が出され、2人の議員(民進・田名部匡代議員、共産・井上哲士議員)による討論を踏まえて採決が行われました。結果は、
白色票(賛成) 百四十九票
青色票(反対) 九十票
で、この動議も可決されました。この①〜③の議会プロセスを踏まえて、本番たる④「中間報告があった本改正案の審議」が最終的に、2名の議員(民進・小川敏夫議員、共産・仁比聡平議員)による質疑と政府側答弁(金田勝年法務大臣、松本純国家公安委員長、岸田文雄外務大臣)、更に4名の議員(民進・蓮舫議員、自民・西田昌司議員、共産・仁比聡平議員、維新・東徹議員)による討論を経て、採決に付されました。その結果は、
白色票(賛成) 百六十五票
青色票(反対) 七十票
で、法案が賛成多数で可決されたということになります。
したがって、以上の立法プロセスを見てわかる通り、少なくとも形式的には、国会法の規定からすると手続き上の瑕疵があると言える訳ではありません。野党側が反発をしたのは、一連の法務委員会での議論の時間や内容を考慮すると、「特別な緊急性」の実質が認められないのではないかという問題だろうと思われます。今回の経緯からすると、通常国会の会期末が迫っていたという事情が「特別な緊急性」に該当すると言えるのか、まずは考えてみる必要がありそうです
この点に関しては、
(二) 中間報告後直ちに議院の会議において審議した例
第十六回国会 昭和二十八年八月四日の会議において、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案につき、労働委員長栗山良夫君から委員会の審査の経過について中間報告があった後、小林英三君外一名提出の「労働委員長から中間報告があった電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案を国会法第五十六条の三の規定により本会議において審議することの動議」が可決され、議長河井彌八君は、直ちに同案を議題としたが、 寺尾豊君の動議により延会することに決した。翌五日同案の審議に入り、質疑、討論の後、同案は可決された。
というケースが参議院での先例とされています(出典:参議院事務局「平成二十五年版参議院先例録」332頁)。
この第16回国会(特別国会)の会期末は昭和28年 8月10日だったので、この時の中間報告は、会期終了日まで「6日」というタイミングでした。
これに対して、今回の国会(193回通常国会)の会期終了日は6月18日。つまり、本日の「中間報告」は会期終了まであと「3日」というタイミングだった訳です。
「特別な緊急性」という要件を、「時間的な切迫性」を重視する観点から考えると、「先例」として引用される案件の半分の時間的猶予と言え、許容されるように思われます。
ただし、「特別な緊急性」を、それ以外の要素、たとえば法案の重要性や、付託委員会における審議の成熟度、上程の必要性、法案を可決・成立させるタイミングに対する社会的期待といった要素も考慮するならば、必ずしも許容されるとは言えないということも可能かもしれません。
しかし、そうした多元的な事情に対する評価はそれぞれです。議院内閣制を前提とする限り、政府与党と野党とで異なる評価があることは当然に想定されます。時間的な切迫性以外の要素については、それこそ、その妥当性を巡って全国民の代表である国会議員が議会で議論して決するべきであり、国会法第56条の3が「議院の判断」に委ねているのはそれゆえではないかと思われますが、いかがでしょうか。